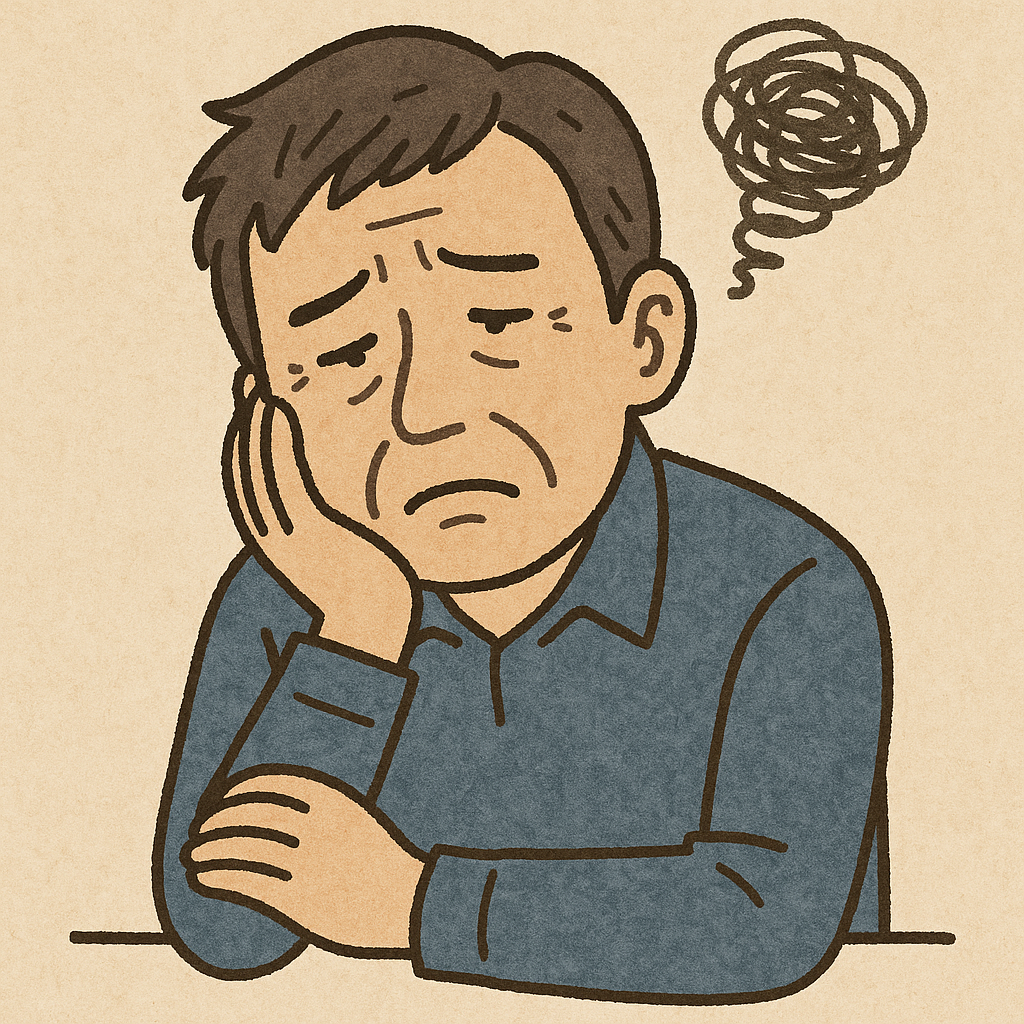2025年6月、年金制度改革を巡って大きな動きがありました。就職氷河期世代への「年金の底上げ」が制度に盛り込まれたものの、当事者たちからは「本当に救われるのか?」「生活できる額ではない」といった本音も聞かれます。本記事では、氷河期世代の現状と年金改革の内容、そして将来への不安についてわかりやすく解説します。
年金改革法案が衆院通過!「底上げ」の中身とは?
2025年6月1日、衆議院で年金改革法案が可決されました。注目されたのは「基礎年金の底上げ」です。これにより将来の年金給付額の低下を防ぐ仕組みが導入されました。
改正のポイント
- 将来的に基礎年金が下がるのを防ぐための措置
- 厚生年金の積立金と税金を活用し、基礎年金を補填
- 次回の財政検証(4年後)で給付水準が下がると予測された場合に実施
この制度により、現状のままだと約30年後に3割減るとされる基礎年金を守ることが目的です。
氷河期世代の実態と将来の年金受給額
1993年〜2004年に就職活動をしていた「就職氷河期世代」は、現在40代後半〜50代半ば。この世代は非正規雇用や収入の低さ、さらには年金保険料の未納などが多く、将来の年金に対して深刻な不安を抱えています。
代表的な声
- 「将来がまったく見えない」
- 「月12万円じゃ生活できない」
- 「生活保護を視野に入れている」
厚生労働省の試算では、改革によって受給総額が最大149万円増えるケースもある一方で、60代以上の一部では23万円減る可能性もあり、評価は分かれています。
支援のはずが負担増?増税への懸念も
制度の改善に期待する声がある一方で、「財源が増税になるなら意味がない」という懸念も根強いです。特に非正規雇用や低所得で生活している層にとって、これ以上の社会保険料や税金の負担増は生活に直結します。
問題点
- 年金の底上げ=厚生年金積立金+税金
- 結果的に「今の若い世代」が将来さらに負担する可能性
- 高齢者世代との「分断」を生むリスクも
「若い人たちを助けるのは当然」という高齢者の声もありますが、制度全体としてのバランスが問われています。
FAQ
Q1: 氷河期世代とは具体的に何年生まれの人ですか?
A1: 一般的には1970年後半~1980年代前半に生まれた人で、大学卒業時に1993年~2004年の就職氷河期を迎えた世代です。
Q2: 今回の年金改革で、どれくらい年金が増えるのですか?
A2: ケースによりますが、厚労省の試算では20年間で最大149万円増加とされています。ただし、個々の就労歴や保険料納付状況によって大きく異なります。
Q3: 増税の可能性はありますか?
A3: 財源の一部が税金で賄われるため、将来的に消費税や所得税の引き上げが行われる可能性はあります。
まとめ
年金改革法案によって、就職氷河期世代の年金がわずかでも増える可能性が出てきました。しかし、「それでも生活できる額ではない」「増税になったら意味がない」といった声もあり、制度の見直しはまだ途上です。現役世代の生活支援と、高齢者支援のバランスをどう取るかが今後の重要な課題となります。